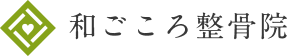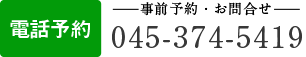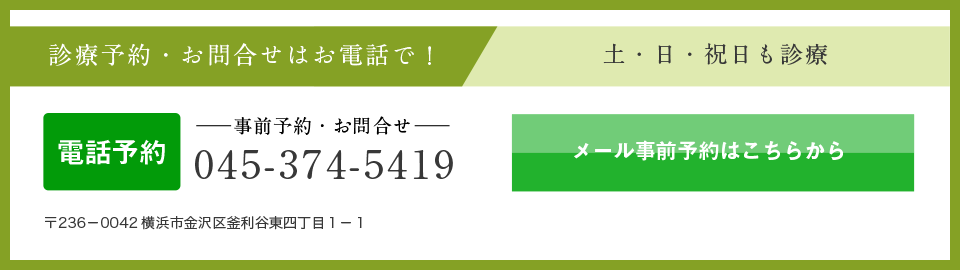実は身近に潜んでいる交通事故。夏休みや年末年始は痛ましい交通事故のニュースが放送されます。
実は身近に潜んでいる交通事故。夏休みや年末年始は痛ましい交通事故のニュースが放送されます。
皆さんが事故を起こしたり、事故に遭ったりすることってめったに、いや殆ど有りませんよね?
しかし実際に出遭ってしまったらどうしますか?
「救急処置の授業受けたから平気!」
「保険入っているから大丈夫だよ!」
本当に対処できますか?
実はかなり身近な事なのに、どうして良いのか分からない交通事故対応について解説します。
交通事故が起きた時の手順
1、負傷者の救助
ご自身や同乗者、相手方に交通事故による負傷者がいないか確認します。
ご自身が動けない、車体に挟まっている場合は救急車を※呼んでもらいましょう。
同乗している家族、相手側が出血や意識が無いなど、余裕があれば自身で救急車に電話です。(補足)交通事故の場合は、救急センターがそのまま警察に連絡してくれます。
※なぜ自分で呼ばないか?
▽意外と動揺しているから です。
場所を聴かれても分からないことが多いので、近くに誰かがいたら「あなた救急車呼んで」と言って呼んでもらい『ご自身は手当て』に回ってください。通報者は名前を聞かれますので、後の証人になる可能性があります。
2、警察への通報
ケガ人がいない場合や軽傷とみられる場合でも、交通事故に出くわしたら必ず警察を呼びましょう。警察官が到着するまでの時間は、お互いの情報をスマホで写真保存します。
相手の連絡先として聞いておくべき項目は、
- 相手の住所、氏名、連絡先(電話番号)
- 相手が加入している自賠責保険、任意保険会社名
- 相手車両の登録ナンバー
- 所轄の担当警察官の氏名
この4つは過失割合や揉めた時に必要になるので必ず撮影&聞いておきましょう。
3、保険会社へ連絡
警察への連絡を終えたら、それぞれの保険会社へ事故の報告を行いましょう。
交通事故の様々な手続きは、基本的に被害者本人と加害者側の保険会社とで行われます。
また、ご自身が被害者でも過失があると(車両が少しでも動いている時点で9:1スタート)被害者側(ご自身)の保険会社を使って損害賠償を支払ってもらう可能性もあるため、被害者が加入している保険会社への連絡も忘れないようにしましょう。
4、病院で診察を受ける
ご自身がケガをされたり、被害者になった時には必ず医師の診察を受けて下さい。特に
「ぶつかったけど、痛くないから行かなくてもいいや」
とその時は何でもなくても、後から痛みが出る事もあります。事故に遭ったことで興奮状態にあるので痛みに対して鈍感になっています。まずは病院で検査してもらい、診断書を出してもらいましょう。
診断書は警察だけでなく、職場、保険会社や整骨院など各関連施設から必要とされます。
その時は原本そのまま提出せずに、必ずコピーを提出してください。
診断書は相手の保険会社や整骨院で治療を受ける際にも必要となります。すべてコピーで通用しますので原本はご自身で保管して下さい。
5、整骨院で治療を受ける
整骨院で治療を受る前に、必ず病院(整形外科等)で検査を受け、診断書を貰って下さい。
事前に相手の保険会社へ
- 受けたい旨
- 整骨院名
- 住所
- 電話番号
上記を伝えて下さい。
後日相手保険会社から受診したい治療院に連絡が来れば、整骨院での治療が可能です。
症状固定とは?
交通事故でのケガが完全に治ったら治療終了となり、加害者側の保険会社との示談交渉が始まります。ところが交通事故によるケガは必ずしも良くなるとは限りません。
もしお医者様がこれ以上治療をしても症状の緩和が見込めないと判断しますと、たとえ痛みが取り切れず残ったとしても「症状固定」になることがあります。
症状固定とは?
その怪我は「後遺症」となり、これまで保険会社が支払ってきた治療費や慰謝料は打ち切りになることを指します。
後遺症になった後も慰謝料の支払いを受けるには、後遺障害と認められて、お医者様から「後遺障害等級」が認定される必要があります。
最後の最後に示談交渉
示談交渉では、被害者に支払われる損害賠償金額について話し合いを行い、お互いが和解・納得すると示談成立となります。
示談が成立すると、加害者側の保険会社から被害者に示談書が送られてきます。被害者が示談書の内容に納得し、署名・押印をして保険会社へ送り返しますと、示談金の支払いが行われます。
ここで、双方納得した上でサインをするのが大切です。
揉めたまま・めんどくさいから・相手側がうるさいからと安易にサインをしてはいけません。悩んだ際は弁護士に相談することが大切です。